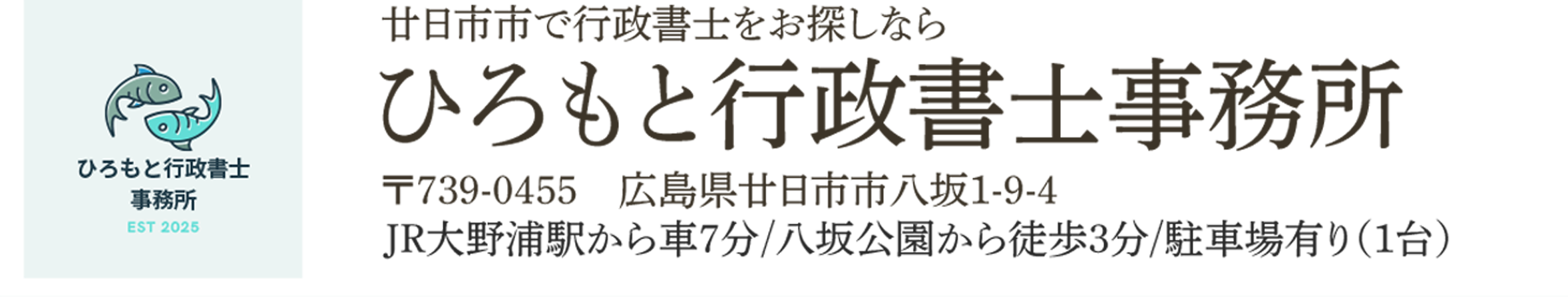配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が、遺産分割の際に一定の条件のもとで、引き続き自宅に住み続けることができる権利です。
制度の趣旨
これまでの相続制度では、遺産分割の際に不動産を単独で相続しない限り、配偶者が自宅に住み続けることが難しくなるケースがありました。特に、配偶者が高齢であったり、十分な預貯金を持たない場合、自宅を売却せざるを得ないケースがありました。
このような事態を防ぎ、配偶者の住まいを守るために、2019年の民法改正により「配偶者居住権」が新設され、2020年4月1日から施行されました。
配偶者居住権の特徴
- 所有権は得られないが、住み続けることができる
- 配偶者居住権は「所有権」ではなく「使用権」に近いものです。
- 不動産の所有権は別の相続人(子など)が持つ場合でも、配偶者は無償で住み続けられます。
- 長期間(終身)または一定期間、居住が可能
- 原則として、配偶者が亡くなるまでの終身にわたり有効です。
- ただし、遺産分割協議や遺言によって一定の期間を定めることも可能です。
- 登記が可能
- 配偶者居住権は登記できるため、第三者(不動産を取得した他の相続人や買主)に対しても対抗できます。
- 遺産分割の際に評価される
- 配偶者居住権の価値は相続財産の一部として評価されます。
- これにより、配偶者は自宅に住みながら、他の相続財産(預貯金など)も取得しやすくなります。
取得方法
配偶者居住権を得るには、以下のいずれかの方法が必要です:
- 遺言による指定
- 被相続人が生前に「配偶者居住権を認める」と遺言を残すことで成立します。
- 遺産分割協議
- 相続人間の話し合い(遺産分割協議)で合意すれば、配偶者居住権を設定できます。
- 家庭裁判所の審判
- 相続人間で合意できない場合、家庭裁判所の判断で配偶者居住権が認められることもあります。
配偶者居住権のメリット・デメリット
メリット
✅ 住み続ける権利が守られる
✅ 自宅を相続しなくても預貯金などの財産を取得しやすい
✅ 登記により第三者に対抗できる
デメリット
⚠ 売却・賃貸などの処分はできない(あくまで「住む権利」のみ)
⚠ 住宅の維持管理や固定資産税の負担がある
⚠ 他の相続人との協議が必要になることもある
まとめ
配偶者居住権は、配偶者が安心して住み続けられるようにするための制度です。ただし、所有権ではないため、売却や賃貸はできず、維持管理の義務もあります。
相続の際には、遺言の作成や遺産分割協議を通じて、適切に配偶者居住権を活用することが重要です。