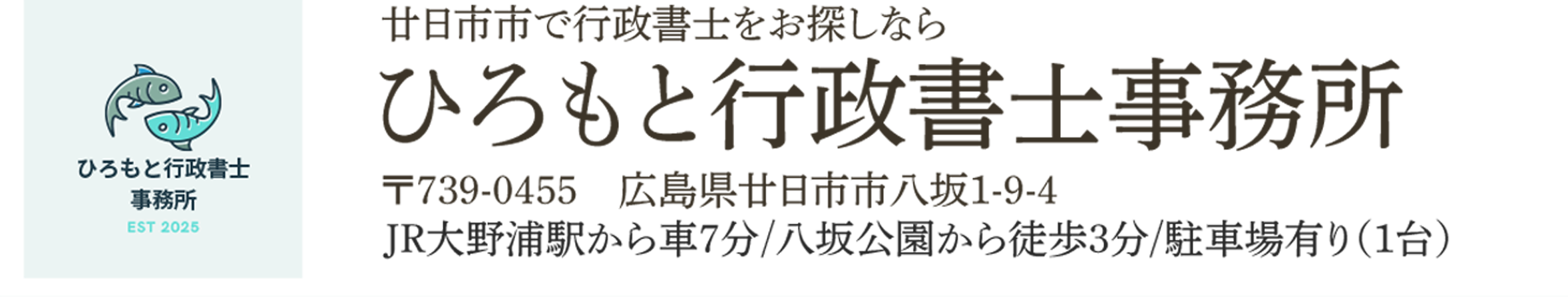相続にはさまざまなパターンがありますが、基本的には法定相続と**遺言による相続(遺贈)**の2つに分かれます。それぞれの具体的なパターンを解説します。
1. 法定相続(民法で定められた相続のルール)
被相続人(亡くなった人)が遺言を残していない場合、民法に基づいた法定相続分に従って相続されます。
① 相続順位
法定相続では、相続人となる人の順位が決まっています。
| 順位 | 相続人の範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者 + 子(直系卑属) | 子がいない場合は次の順位へ |
| 第2順位 | 配偶者 + 直系尊属(父母・祖父母) | 子がいない場合のみ発生 |
| 第3順位 | 配偶者 + 兄弟姉妹 | 子・直系尊属がいない場合のみ発生 |
| 番外 | 内縁の妻・夫、養子縁組していない人 | 法定相続人にはならない |
💡 配偶者は常に相続人となる(ただし、内縁関係は除く)。
② 法定相続分(相続人ごとの取り分)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子(1人 or 複数) | 1/2 | 子全員で1/2を分割 |
| 配偶者 + 直系尊属(父母・祖父母) | 2/3 | 直系尊属全員で1/3を分割 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4を分割 |
| 子のみ(配偶者なし) | なし | 子全員で100%を分割 |
| 直系尊属のみ(配偶者なし) | なし | 直系尊属全員で100%を分割 |
| 兄弟姉妹のみ(配偶者なし) | なし | 兄弟姉妹全員で100%を分割 |
💡 兄弟姉妹が相続する場合、異父・異母兄弟の相続分は半分になる。
2. 遺言による相続(遺贈)
被相続人が遺言を残していた場合、遺言の内容が優先されます。
ただし、遺留分(最低限の取り分)があるため、完全に自由に分配できるわけではありません。
遺言の種類
- 自筆証書遺言:自分で書く(法務局に保管可)
- 公正証書遺言:公証役場で作成(安全・確実)
- 秘密証書遺言:秘密にしたい場合(あまり使われない)
💡 遺言がある場合でも、遺留分を侵害するとトラブルになる可能性がある。
3. 相続放棄と限定承認
相続人は相続を必ずしも受け入れる必要はなく、以下のような選択肢もあります。
① 相続放棄
- すべての財産を放棄(プラスもマイナスも受け取らない)
- 家庭裁判所に申立てが必要(期限は3か月以内)
- 次順位の相続人に相続権が移る(子 → 親 → 兄弟姉妹の順番)
② 限定承認
- プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続(負債を超えない限り責任を負わない)
- 相続人全員が一致して申請する必要がある
- 家庭裁判所に申立てが必要(期限は3か月以内)
💡 借金などの負債が多い場合は相続放棄や限定承認を検討するのが一般的。
4. 特殊な相続パターン
① 代襲相続
相続人(子や兄弟姉妹)がすでに死亡している場合、その子(孫や甥姪)が相続する。
例:
- 父が亡くなり、本来相続人である長男もすでに死亡 → 長男の子(孫)が相続人になる。
💡 兄弟姉妹の場合は、甥・姪まで代襲相続が可能(再代襲はなし)。
② 特別受益と寄与分
- 特別受益:生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合、相続分を調整する。
- 寄与分:介護や家業への貢献があった相続人は、相続分を増やせる。
5. まとめ
✅ 法定相続:配偶者+子、親、兄弟姉妹の順で相続が決まる
✅ 遺言がある場合:原則、遺言が優先される
✅ 相続放棄や限定承認:借金が多い場合は検討
✅ 代襲相続や特別受益・寄与分:特殊なケースでは相続分が変動
相続は法律が絡むため、トラブルを防ぐには遺言を作成したり、専門家に相談するのがベストです!
4o